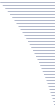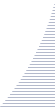| 村松弘康 | |
|
○強さを求める時代  昨年1月25日、北大法学部で「21世紀の司法改革はどうあるべきか」の特別講義を終えた後、中川教授の部屋で会った○○君から、手紙が送られてきた。その中に、ナーウェンの著書「Thepathofpower」の「訳者あとがき」のコピーが同封してあった。 医者でもある訳者はこう指摘している。「今日は強さを求める時代である。また、強くなかったら生きていけないかのように言われてしまう時代である。だから弱さは極力、忌み嫌われるものとなり、人々の間からその存在が抹殺されかかっている。」 更に訳者は、スイスの精神医学者P.トゥルニエの言葉を引用し、強さ万能の社会のあリ方に強く異議を申立てる。すなわち「現代文明の病気は力への暴走と捕らえることができる。すなわち、ルネサンス以来人間の願望・欲望に火をつけ、力こそは最高の価値となり、晋遍的に認められる唯一の価値となった。しかし、その結果、我々の文明は傲慢以外の何ものでもなくなり、多くの破壊と生活内容の貧困をもたらした」と。 ○市場競争自己責任 経済評論家の内橋克人氏によれば2001年国連ミレニアム宣言は、世界に広がっている危機を ①国家の衰退から国家の退却へ ②世界をおおうネオプランテーションとでも呼ぶべき「植民地単作経済」の深化 ③世界市場化の怒涛 ④公共の市場化にあると分析したうえで、人類に必要な価値は自由、平等、連帯、平和、民主主義であると定義しているのだという。 日本も例にもれず規制緩和、自由競争礼賛の大合唱の中で市場と競争と自己責任任を強調しながら21世紀を迎えた。市場による競争万能の原理は、国家のみならず広く社会における公的なシステムを私的システムヘと急速に代替していくに違いない。 市場による機会の平等の拡張が巨大な結果の不平等を正当化し、自己責任の名の下で競争の結果に対する異議申立が不可能となる社会がこれから目指すべき社会であろうはずがない。 司法改革の議論もまたその流れの中にあり、司法制度改革審議会での議論は、これからの時代、国民は統治客体から統治主体へと移行しなければならず、競争社会を生き抜くためには自己責任を自覚しなければならないとし、司法は競争における敗者に対する事後救済機関としての役割を果たすことになると位置づける。 すなわち、司法の場でも、強者が勝ち残り、弱者が敗れていく社会システムを支えるための司法制度が構想されているのである。 私は、ここ数年間、日弁連司法改革推進センターの副委員長(2001年度は司法改革実現本部副本部長)の立場で司法改革問題という窓から日本の社会の有り様を眺める機会を得たが、競争システム礼賛者の声高な主張に対する違和感はやはリ強まるばかりである。 ○凍結された財産 P.トゥルニエは、鋭くこう指摘する。「私たちの相談室には、現代社会の中のいろいろな犠牲者が来てはまた去っていく。それは豊かなパーソナリティの持ち主であったり、芸術的な人、敏感な人、生産的な想像力を持った人の場合が多く、彼らは敗北者としてやってくるのである。しかし現在人類が必要としている親切、良心、情緒、感受性、美、直感といった<凍結された財産>は、合理主義者や技術的現代文明が蔑んでいるこれらの人たちの中に、深く眠っているのである。」(「強い人、弱い人」ヨルダン社186頁)。 20世紀はテクノロジーが巨大に発達した時代であった。我々は多くの物質的な便利さを手に入れることが出来た。しかし、便利さは、私達の身体を甘やかし、本来備えていた野性的直感を眠らせた。明日も無事生きられるのだろうかという生存の不安は、今日の命を祝福し輝かせた。生きることそれ自体の不確実さは、命のつながリと人間の連帯の必要を否応なしに自覚させた。 テクノロジーの発達によって眠ってしまった私たちの原始の身体感覚を、会こそ覚醒させなければならない。人間であるとは如何なる存在であるのか。いのちは如何にして輝きを得ることができるのか、今こそ原点から出発しなければならない。 ○自閉と反撥 経済競争における強者・勝者が人間的に豊かで、優れている保証はどこにもない。人間を評価する基準を-元化することは、個が生まれながらに備えている多様な価値を否定しかねない。否定された多様な個、あるいは個性は、社会的には無価値なものとして無視され、否定され、抹消される。無意味・無価値なものとさげすまれた者にとっての選択の道は、多くの場合、個の内側に深く自閉していくか、外に向かって強く反撥し異議を申立てるかのいずれかの道しか残されていない。自閉と反撥は、孤独と不安に満たされた混沌とした暗い河を流れ、時として暴発する。 個の暴走は何も子供に限ったことではない。子供が友達や親を殺し、行きずりの人、障害者を襲うだけでなく、大人も弱い対象に向かっていく。母親も子供に暴力をふるい、時には殺す。男達も、妻・子供に想像を絶する暴力を加え、家族は暴力の温床となり果てる。暴力は、時には人間以外の動物にも向けられる。調教名目で象に暴力を加え死に至らせた男達、ウサギや犬、猫などのぺットや、猿、熊、キツネ、エゾ鹿などの野生動物に対する理不尽で人間本位・経済本意の殺戮・虐待は、日常の風景とさえなりつつある。 競争が激しければ激しいほど、選別が激しければ激しいほど、敗者の烙印は重くのしかかり、かつ致命的にまで個を追いつめ、人間を過剰な暴力へと駆り立てる。 ○咲く 学生が同封してくれていたコピーの中に久野信さんの「子育ての風景画」があった。「あなたの手は何をつかんでいるの」と題する文章の中には、「すべての人は、自分の花を咲かせたいという自己実現の欲求と、そのために必要な力を、すべて備えています。」とあった。この言葉はこれからの社会の有り様を鋭く示唆している。 生きとし生けるものすべては、1つしかない個性という名のつぼみを持ってこの世に生まれてきた。陽があたり、温められてはじめて、つぼみは咲いていいのだと気付くことができる。北風や吹雪の中では咲けない。褒めて、励まして、温めて、やっと咲けるのだ。それも自分だけの力だけでは十分には咲くことができない。他人の力が必要なのだ。 生咲けないまま、つぼみのまま終わってしまったら、この地球に命を授かった甲斐がない。咲けなかったつぼみは悔しさをその実いっぱいに詰め込んで、のたうち回りながら、叫びながら、号泣しながら、この世から去っていったに違いない。咲きたいけれど咲けない。その悲しいエネルギーが自閉と暴走の源(みなもと)だとしたら、その可能性が万に一つでもあるのならば、私たちは、やはり立ち止まらなければならない。我を忘れてここまで走り続けてきて、このあと走り続けてどこへ行こうとしているのか。忘れ物はなかったか。みんなが走っていくからといって、無理して、あわせて走ってきたに過ぎなかったのではなかったか。今こそ、立ち止まって、これからの100年を考える勇気を持たなければならない。 ○木漏れ日のような希望 「俺は急がない。おれは時々立ち止まる。そして雲を見たり、草の露、木の葉の露を見たりするんだ」という詩がいいと山田洋二監督はいう。 監督はその詩を「十五才学校Ⅳ」で使った時のことをこんな風に表現している。 「今度の『十五才学校IV』という映画で詩を語るところがあるんです。引きこもりの少年が不登校の少年と友達になって、彼に贈った詩なのだけれど、浪人に自分をなぞらえて、みんなは馬で走っていくけれども、おれは歩いて行く。時々立ち止まる。そして雲を見たり、木の葉の露を見たり、そしてまたゆっくりと草原を歩いていく。 僕は急がないという詩なんです。 その詩は、小学校の4年生からずっと不登校の、今17歳の女の子が書いた詩です。浪人が主人公の詩だけれど、娘さんの詩。 その詩が観客に人気があるんですね。あの詩がいいと中学生たちが言ってくれます。それはかすかな木漏れ日のような、希望なんです。『おれは急がない。おれは時々立ち止まる。そして雲を見たり、草の露、木の葉の露を見たりするんだ』という。 主人公の少年は長い旅をするんだけれど、田舎町にあるトラツクの運転手さんの家に泊めてもらったら、その家に引きこもりの少年がいる。ほとんど表に出なくて太ってしまったような少年。 その部屋に泊まって少年同士はいろいろな話をする。別れ際に彼が久しぶり、何年ぶりに表に飛び出してきて主人公の少年にジグソーパズルを完成させたものをプレゼントするんです。その裏にこの詩が書いてある。それを主人公がお母さんに読んで聞かせてやる。そうするとお母さんが運転しながら泣き出すという話なんです。」(法律時報増刊 シリーズ司法改革Ⅱ 12頁) かすかな木漏れ日のような希望だけれど、確かな希望に、私たちは21世紀日本の未来をかける。 残されている時間は決して長くはないから、少しの時間立ち止まって話をしてみないか。たとえば引きこもりの少年と人生の忘れ物や、人間の優しさについて・・・。 |