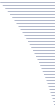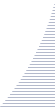| 土屋 朋子 | |
|
新幹線の車中で駅弁を買おうとしたときのこと。若い女の売り子さんが、私の問いかけに答えて、「うにとイクラの..」「ホタテも入って」「鮭とイクラが..」と早口でまくしたてる。  当方としてはせっかくの一食、どれでもいいというわけにはいかない。量は少な目がいいなとか、ホタテはどんなスタイルで入っているのだろうなどと思いを巡らし、納得した上で選びたい。当たりはずれは時の運。選択眼がなかったとあきらめるしかない。若い売り子さんは、そんな思いで品定めする私に、「どれにしますか?」の一点張り。早く決めてほしいという態度がありありだ。そうだろう。早く、たくさん売ることを義務づけられているのだから、こうした態度も当然といえば当然で、なにも私に文句をつけられるようなことをしているわけではない。つまり彼女としては、そのように教育されてきたことを忠実に実行しているだけなのだ。 しかし、日本人は、いつからこうなってしまったのだろう? ◆ 87才になる母が、脳こうそくのリハビリと避寒を兼ねて入院している。久しぶりに様子を見るため、山陰に帰ってきた。昨年、鳥取西部地震の震源地になった私の故郷は、今も修復作業のためにごった返している。病院では、看護婦さんがとてもよくやってくれるのだが、何か違うのである。野菜のおかずを残す母に、「がんばって、残さないように食べようね」などとは、当然のことながら言ってくれるはずもない。 リハビリも形だけ。私がていねいに、その運動の意味とやり方を教えると、「ああそういうことなのね」と納得。そういった理解力は、未だ充分に残っているのだ。(暖かくなったら、できるだけ早く退院させようと決めた。まだら模様に、加齢からくる機能の低下が現れはじめているが、それを気遣っての至れり尽くせりは、むしろ老化を早めるだけと思ったからだ..。しかし、地域のコミュニティが、昔に比べて希薄になっているのが心配の種である。) だからといって、病院のスタッフたちに文句を付ける気は毛頭ない。誰もが忙しく立ち働き、スケジュールをこなすのに精一杯なのである。決められた以上のことをやる余裕はどこにもなさそうに見える。人の命を預かる病院がこうなのだ。 日本は、いつからこうなってしまったのだろう? ◆ 政治の場で、突如として教育改革が叫ばれ、ボランティアの制度化や、様々な教育制度の見直しが検討されようとしている。あのうす汚れた政治家たちが、教育の重要性とやらを語れば語るだけシラケてしまうのは、私だけではないはずだ。「教育」とは子供たちのためだけにある言葉ではない。こんな子供たちを育ててきた責任は、どこにあるというのだろう?子供たちの問題はすべて大人たちの問題だ。大人たちが構成する社会の問題なのである。  しかし、制度を変えれば何とかなるというものではないだろう。今の状況では、悪くなりそうな予感の方が大きい。 ◆ TVの番組で、生まれた瞬間の血のついた赤ちゃんをお母さんの胸に置き、母と子の最初のコミュニケーションを大事にする病院の取り組みを見た。人間も動物なのだと、改めて実感する。そのドクターは、「何にも代え難い、その瞬間を大事にしたい。赤ちゃんの体重を量る、目の消毒をするなどといったことは、その後でもいいのだ」と語っている。 この病院では、生まれた時からすぐの、母子同室をすすめている。普通、生まれたばかりの赤ちゃんは、万全の体制を整えた新生児室に入れられて、退院の時にお土産のように頂いて帰るケースが多い。新米のお母さんが、誰の助けも期待できない家に帰った時、この小さな生き物をどう扱ってよいかわからなくて苦労するというのは、よく聞く話である。 生まれた時からすぐに、赤ちゃんを自分の側において世話をする母子同室のシステムは、いってみれば昔からのやり方なのである。想定できるリスクを補うだけのメリットがあると考えて、こうしたやり方を押し進めるドクターの取り組みが、こうしてTV番組に取り上げられるほど、今の管理体制は強固なものだということなのだろう。 「管理、管理、管理!」チャップリンの古い映画、ベルトコンベアーに踊らされる人間を描いたシーンを思い出す。私たちは「管理する」「される」という視点に何の疑いを差し挟むことなく、長い時を過ごしてきたようだ。 教育のシステムこそは、その最たるものではなかろうか。21世紀に入ってもなお懲りもせず、教育制度が、新しい衣をまとった管理体制に入れられようとしているなんて! 「教育」という言葉を「育てる」という言葉に置き換えてみると、教育は、学校の中にだけあるものではないことがよくわかる。 土屋 朋子 Plus-Press No.81 2001.3.26より |