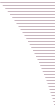| 松原 武士 | |
 通常の意識活動として認識されているのは、無意識から浮上している顕在的な意識現象だと思われる。しかし、人間の意識の下部にはとてつもなく深い無意識の部分があり、本当の目的は其処のところで眠っている。ユングが表現した元型といわれる本質的な部分だ。人間の一生を通じて演じられる人生というドラマでは、その元型を浮上させて自分という存在を表現することを目的としている。個人が生きる目的を持って生まれてきたにもかかわらず、生涯を通じてそれを明らかにできない人間が圧倒的に多い事実がある。人生という舞台ではそれを求める試行錯誤で満ちている。 通常の意識活動として認識されているのは、無意識から浮上している顕在的な意識現象だと思われる。しかし、人間の意識の下部にはとてつもなく深い無意識の部分があり、本当の目的は其処のところで眠っている。ユングが表現した元型といわれる本質的な部分だ。人間の一生を通じて演じられる人生というドラマでは、その元型を浮上させて自分という存在を表現することを目的としている。個人が生きる目的を持って生まれてきたにもかかわらず、生涯を通じてそれを明らかにできない人間が圧倒的に多い事実がある。人生という舞台ではそれを求める試行錯誤で満ちている。その個人的な人生が集大成された歴史的なドラマのなかでも、人間の持っている意識の元型が表現されている。ある意味で個人的な人生の記録より、歴史という過去の記録のほうが間接的ではあるが、人間の元型的な目的があからさまに表現されていることがある。人間が表現しようとあれこれ悩んだ生きる目的が、あっさりと歴史という人間集合の経験的な記録上に露呈しているのだ。60年代にはそのような歴史的な元型が浮上していた。 歴史とは人間の集合的な意識活動であり、それらの意識活動の結果に集合的な無意識が被さった記録だ。意識と無意識が余儀なく表現された人間の行動様式の結果が、歴史という名で記録されてきた。そのような様式で構成された舞台の上で演じられた奇人的な行動が、積もり積もって過去から現在に至る人間劇場を提供してきたと言える。 「歴史的な視点から見て、60年代とはどの様な時代だったのだろうか」 決定的なパラダイムシフトを人類に提示した、本当の意味で歴史的なタ−ニングポイントに当たる時代だった。あの頃から何もかもが変わり、それまでの日々が急速に色褪せた転換点のような気がする。ラジオがテレビに変わり、テ−プレコ−ダ−とコピ−機器とビデオコ−ダ−の普及で、表現手段と記録する行為が個人的な手段になった。タイプライタ−はワ−プロに駆逐され、八ミリカメラはビデオカメラの即席的な再生技術の前に消えていった。画期的なLPはあっと言う間にCDに変換され、何時でも好きなままにMDとうディスクに殆ど原音に忠実に録音できる。何かもがあっと言う間に変化した時代だろう。 自動車は各家庭に行き渡り、誰もが飛行機で海外に飛び出せた、一昔前なら夢のような生活をいとも簡単に実現でき、貧乏人も金持ちもある意味では一気に近づくかの様な錯覚を共有できた、理想的な時代に向かっていると思えた時代だった。その楽天的な発展感覚に対して疑問が生まれるとすれば、物質的な資源とエネルギ−の枯渇にあった。人口の増大とか貧富の拡大とか精神的な荒廃が問題になるとはあまり思っていなかった。というよりも科学の能力を信じていた。60年代における科学への信頼性は宗教的なモノだった。 人類にとって歴史的な出来事が発生した時代は、かなり強い印象を潜在意識に残すらしい。それは一種のカルチャ−ショックという心理的記録として刻印され、文化や生活様式を変化させてきた。自然の力に頼って生計を立てていた採取と狩猟の生活は、農耕と定着する生活の便利さに勝てなかったし、都会文明と貨幣経済が作り上げた科学的生活に農耕文明は機械化する他はなかった。科学的な機械化文明は人類という種を根底から変化させた。中世がルネッサンスを経て植民地時代に至ったより大きい変化が、20世紀という激変の時代における60年代にあったことを認める時代に来ている。その事実をまとめる世代は団塊の世代に他ならない。 団塊の世代という人類の特殊性は、60年代に青春を過ごせたことにある。誰もが時代が激変する瞬間に生きられるわけではなく、限られた世代のみが宝くじに当たる確率で輪廻転生しながら、何とかやっとの思いで選択された結果として経験できる。ソクラテスやダビンチやモ−ツアルトも、団塊の世代と同じようにラッキ−な人達だったと思う。彼らだってあの頃の歴史的な激変期に生まれなければ、ただの変わり者でしかなかったろう。僕も含めて団塊の世代人類は変わり者が多く、いつも社会システムから溢れ出てあまされていたはみ出し集団多かった。世の中のはみ出し者だった気がする。 つまり人類の歴史始まって以来の殺戮が行われた第二次世界大戦の落とし子であり、絶望と希望のせめぎ合う隙間に生まれたのが団塊の世代だった。受験でも就職でも常に間に合わせのプレハブ仮設施設のような環境におかれ、社会は我々が通りすぎるのを我慢していたような雰囲気を味わって育つ。歓迎されなかったのに、やたらと仲間人数が多かった。同時にライフスタイルが突然変わり、家族制度とか日本人としての堅苦しい人間関係も激変する。自由と民主主義が素晴らしい制度として受け入れられ、あたかも本当に正義と真実が社会基準として受け入れられると思い込んでしまった。一億総白痴化シンドロ−ムに罹ったかのように、未来をバラ色にしてしまう時代が近未来バブル経済の土壌になる。  20世紀に生まれたということは、過去の歴史的体験が突然変化した事態に遭遇したということだ。工業化という機械文明は電気と内燃機械を家庭の中に引き込み、個人的な生活体験において科学的な進化を味あわせてくれた。それ以前の時代とそれ以後とでは次元が全く違う、新しくて未知なる先が読めない時代へと人間を急き立てた気がする。誰もがその加速された時代的進化を止めることが出来ず、ひたすた世の中の移り変わりに後れを取るまいと必死に生きてきたのだ。このままではトンでもないところまで行ってしまう、そのように叫んだ人々もいたが所詮はアウトサイダ−の警告でしかなかった。狼が来る! そして遂に狼が姿を現したが、誰もがそのことを認めようとはしない。かなり恐ろしい事態になろうとしているのに、見てみないふりをしてやり過ごそうとしているようだ。しかし確実に狼は牙を向いて襲いかかろうとしている。大人よりも子供たちが素直にその事実を認識している。将来は明るくなるどころか、大人たちが取った選択肢は最悪だという 20世紀に生まれたということは、過去の歴史的体験が突然変化した事態に遭遇したということだ。工業化という機械文明は電気と内燃機械を家庭の中に引き込み、個人的な生活体験において科学的な進化を味あわせてくれた。それ以前の時代とそれ以後とでは次元が全く違う、新しくて未知なる先が読めない時代へと人間を急き立てた気がする。誰もがその加速された時代的進化を止めることが出来ず、ひたすた世の中の移り変わりに後れを取るまいと必死に生きてきたのだ。このままではトンでもないところまで行ってしまう、そのように叫んだ人々もいたが所詮はアウトサイダ−の警告でしかなかった。狼が来る! そして遂に狼が姿を現したが、誰もがそのことを認めようとはしない。かなり恐ろしい事態になろうとしているのに、見てみないふりをしてやり過ごそうとしているようだ。しかし確実に狼は牙を向いて襲いかかろうとしている。大人よりも子供たちが素直にその事実を認識している。将来は明るくなるどころか、大人たちが取った選択肢は最悪だという事実を、彼らは冷めた視線で眺めている。それゆえこのまま行き着くところまで行こう。何もかもが破壊されたそのあとに、本当の意味で新しい世界が開ける。そして遂に学生運動が世界中で始まり、いても立ってもいられない衝動に突き動かされ、アルバ−ト・アイラ−のように破壊しまくった。それが60年代だったような気がする。 人類が未曾有の経験をする前兆現象として、60年代は歴史的な予告編を現象化させたのだろうか? 2000年を生きるにあたり、その当時のことを考えることで何かが見えてくるかもし れない。そのような気がしてならないのは僕だけであろうか。他のたくさんの人々の感じた60年代感を聴かせてください。 |