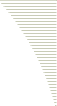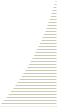| 佐々木 亜弓 | |
|
バイオダイナミック・ブロードキャスター実験レポ−ト
実験実施者:佐々木亜弓 実験協力者:狩野謙二 (狩野自然農園農園主) 1.実験題目 バイオダイナミック農法による収量向上及び土壌回復促進の実効性の検証 2.実験期間 平成12年10月より平成13年8月まで 3.要 旨 バイオダイナミック調合剤(ルドルフ・シュタイナ−提唱)の振動情報をパイプ装置によって農地に与え、同時にバイオダイナミック・カレンダ−を使用することにより、いかに農作物の収量を上げ、土壌を短期間に回復させられるかを実験区と対照区を設けて実験した。 4.目 的 収量を減らすことなく慣行農業(化学農薬・化学肥料・化学除草剤等使用)から有機農業への転向を可能にする農法の一つがバイオダイナミック農法であることを実証するため。 5.方 法 1)実験区(バイオダイナミック区)、対照区(非バイオダイナミック区)を約500m2ずつ設け、両区の間に300m2の緩衝区を設けた(下図参照) 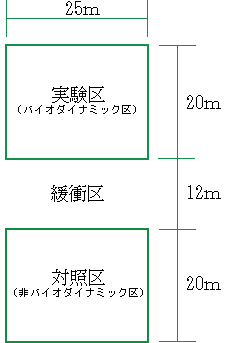 ※実験農地の所在地:岩見沢市稔町839−1 ※実験農地は平成12年9月まで40年以上農薬、化学肥料、除草剤等が使用されていた。昭和40年代までは主に米、以降は玉ねぎが栽培されていた農地である。有機農業を営む狩野謙二氏が平成12年9月に同実験農地を購入し、翌月の10月に比較実験を開始した。 2)実験区、対照区ともに同量の緑肥及び魚粕を平成12年10月に施肥して条件を同一に整えた。尚、緑肥は狩野自然農園の雑草を土にすき込んだ。 3)平成13年5月1日に実験区(バイオダイナミック区)のみにバイオダイナミック調合剤の振動情報放射を開始した。比較のため対照区及び緩衝区にはパイプ装置による情報放射は行わなかった。 ※同パイプ装置はラジオニクス原理に基づいて開発されたもので、詳しくは同報告書提出者にお問い合わせください。 E−mailアドレス:ana07968@nifty.com 4)作物の種まきや苗の定植は以下の日程(いずれも平成13年)で行った。 作付けした作物は玉ねぎ、大根、小松菜、白菜、サラダ菜で、実験区と対照区に同量ずつ作付けした。 5月2日 対照区に玉ねぎを定植 5月15日 午後3時に実験区に玉ねぎを定植、大根を直播 5月16日 対照区に大根、小松菜を直播 5月18日 実験区に小松菜を直播き 6月2日 実験区に白菜、サラダ菜を直播 6月3日 対照区に白菜、サラダ菜を直播 上記日程はバイオダイナミック・カレンダ−(`種まきカレンダ−´)に従って決定したもので、実験区ではカレンダ−の指示通りに天体の動きに合わせてその時々に適した作物の農作業にあたった。 対照区では比較のため意図的にカレンダ−の指示に逆らってその時々に適さない作物の農作業にあたった。 ※`種まきカレンダ−´は熊本県阿蘇のぽっこわぱ耕文舎発行のもので、毎年出版されている。 連絡先:Tel 09676-7-2479 6.結 果 平成13年8月15日、各区内の中心位置180cm ×90cm の範囲部分より収穫し比較した結果を下記に示す。 1)玉ねぎの収量比較 実験区 総個数37個 サイズ内訳 L 27個 、 M 6個 、 S 4個 対照区 総個数39個 サイズ内訳 S 30個 、 SS 9個 ※各区の面積当たりの収穫量から10アール当たりの収量を算出すると 実験区 4,006kg 対照区 1,485kg である。 2)玉ねぎの重量、直径、糖度の比較 前述の範囲部分から収穫した玉ねぎの内,各区の中心位置50cm ×30cm の範囲から、それぞれ収穫された10個について重量、直径、糖度を測定した結果を示す。(写真参照) ※実験区(バイオダイナミック区) 番号 重 量 直 径 糖 度 1 180g 72mm 11
2 230g 81mm 8 3 300g 77mm 11 4 130g 65mm 7.5 5 205g 72mm 10.5 6 225g 79mm 9 7 240g 79mm 9.2 8 165g 74mm 7.2 9 115g 62mm 6.5 10 165g 72.5mm 8.8 平均値 195g 73mm 8.8 ※対照区(非バイオダイナミック区) 番号 重 量 直 径 糖 度 1 75g 53mm 8 2 60g 50mm 5 3 50g 45mm 4.5 4 110g 60mm 7 5 95g 56mm 5.5 6 60g 46.5mm 8 7 40g 40mm 6.8 8 60g 48mm 8.2 9 55g 48mm 4.5 10 30g 38mm 7.5 平均値 63g 48mm 6.5 3)糖度比較(上述の10個の平均値) 実験区 8.8 対照区 6.5  4)土壌分析結果 同実験農地では平成12年9月まで農薬その他が使われていたため実験区、対照区の残留農薬濃度を現在比較分析中。 5)生育過程比較(7月14日現在 写真参照) ・対照区に比べて実験区に玉ねぎを約2週間遅く植えたにもかかわらず、7月14日の時点では実験区の玉ねぎの葉の生育が対照区の玉ねぎの葉の生育を上回った。 実験区の玉ねぎの葉は青々としてほぼ垂直に伸びていて生育が旺盛であったが、対照区の玉ねぎの葉には黄色が目立ち、水焼けの影響を差し引いても生育がかなり悪かった。 ・サラダ菜の発芽率は実験区は10分の7だったのに対し、対照区は10分の1という結果だった。 ・対照区においては大根、小松菜の発芽はまったくみられなかった。 ・白菜は実験区では均一に発芽し、生育も良好だったが、対照区の白菜は発芽が不揃いで生育も遅かった。白菜のサイズも実験区の方がかなり上回っていた。 実験区 対照区   7.考 察 実験1年目にして実験区と対照区に予想を上回る大きな差がみられた。特に収量の点では目を見張る違いがあった。来年以降も同様の実験を行い観察を行う必要がある。今後も同様の結果が得られれば既存の化学農薬農業を行う農業者が有機農業に転向する上でこのバイオダイナミック農法が大きな助けになる可能性が大いにある。 |